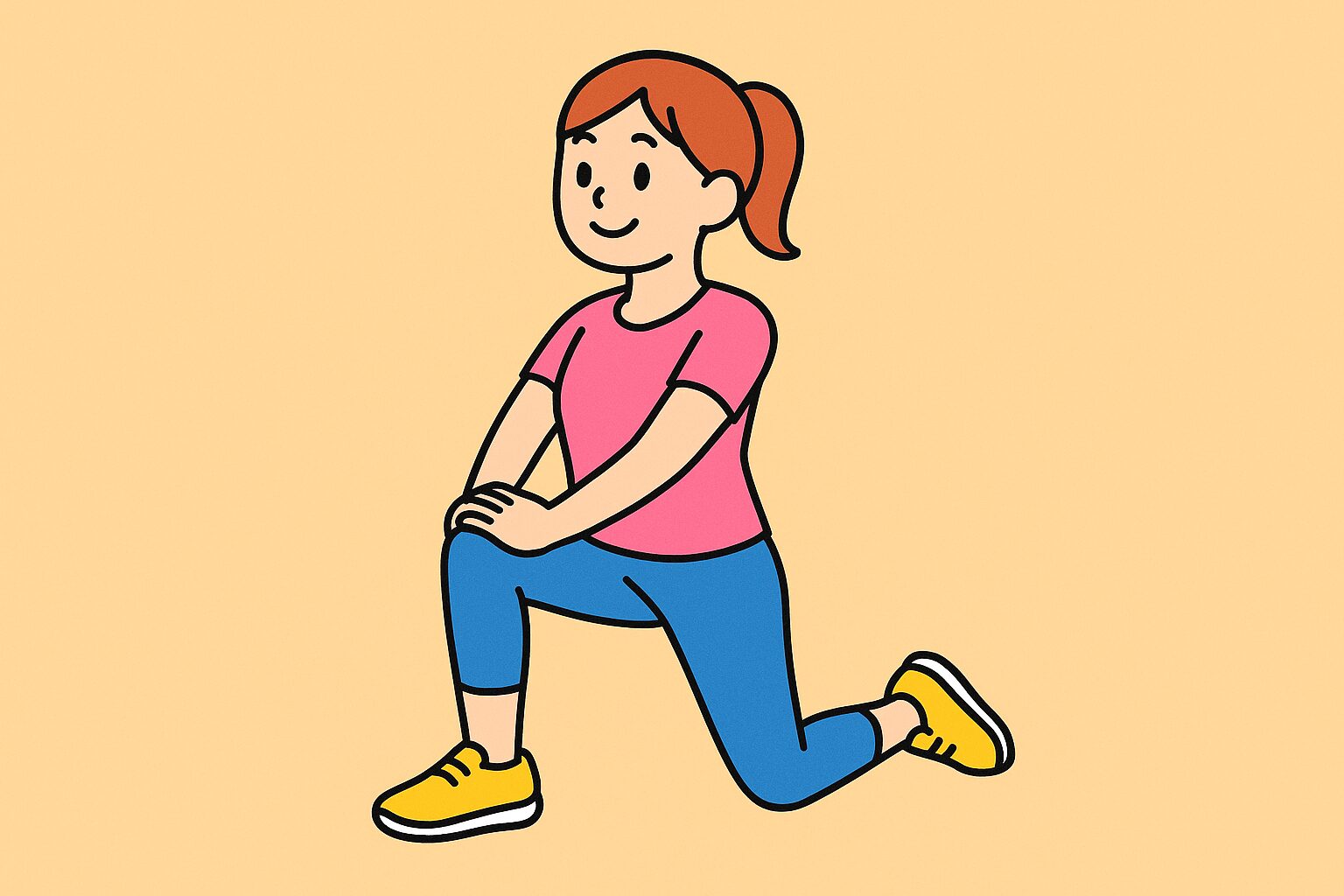冷えが坐骨神経痛に与える影響
気温が低くなると、身体から熱を逃がさないために血管が収縮して、体温を一定に保とうとする機能がはたらきます。一方で血液の循環が悪くなる、筋肉が硬くなるなどの影響もあり、結果的に坐骨神経痛の痛みが増します。
血液は、身体のあらゆる部位へ栄養や酸素を供給する重要な存在です。血管の収縮で血液の循環が悪くなると、酸素供給も低下します。
酸素の供給が鈍くなれば、痛みを引き起こす疼痛物質(ブラジキニン など)が筋肉にたまりやすくなり、坐骨神経痛の悪化を招くことも考えられます。
坐骨神経痛を改善する冷え対策
坐骨神経痛は、腰周辺に起こる神経痛です。足先など下半身の冷えを軽視していると、心臓との間に位置する腰にも影響が出ます。坐骨神経痛に悩んでいる方は、日頃から身体の冷えに注意しましょう。
ここでは、おすすめの冷え対策を7つ紹介します。
暖かい衣類を身に着ける
身体を冷やさないために、暖かい衣類を身に着けることが大切です。外出する場合、スカートやパンツの下に1枚増やす程度でも冷えのリスクを軽減できます。ボディラインを崩したくない方は、スカートやパンツの下にスパッツやタイツを追加する方法がおすすめです。
ストールやブランケットの活用も効果的です。最近は些細な動作では落ちにくい、身体に巻き付けるタイプのブランケットなども販売されています。十分な厚みがあるものや、使用シーンに合った形状のものを選びましょう。
ほかにも、腰に貼るタイプのカイロを使用したり、腹巻きを身に着けたりする方法もあります。
ゆっくりと入浴する
全身を温める方法として、時間をかけた入浴も効果的です。手足はもちろん身体の中心も一度に温められる入浴は、血液循環を良くするため、症状を和らげることが期待できます。
入浴で身体を温めるときのポイントは、バスタブに十分なお湯を張り、しっかりと時間をかけてつかることです。熱いお湯に短時間のみ浸かる方法や、シャワーのみで済ます入浴は、身体が温まりません。
ぬるめのお湯にゆっくりつかり、手足や身体の芯まできちんと温めることが大切です。ただし、温めすぎると痛みが増す可能性があります。無理をせず、適度な入浴時間にとどめましょう。
適度に身体を動かす
外出する機会が少なくとも、適度に身体を動かす習慣作りが必要です。デスクワークが多い方や、リビングで長時間座って過ごすことが多い方は、同じ姿勢が続きがちです。長時間同じ姿勢を続けると、血液の循環が鈍り、腰痛や手足の冷えにつながります。
同じ姿勢を続けることが多い方は、定期的にストレッチや軽い運動をしましょう。本格的なストレッチや運動が困難な場合でも、トイレや休憩のタイミングで身体を動かせます。立ち上がって伸びをしたり歩いたりする程度でも、血流を改善して筋肉をほぐせます。
正しい姿勢で過ごす
正しい姿勢を意識して過ごすことも、神経痛の痛み対策になります。寒い季節は血管のみならず、身体そのものも縮こまって体温の放出を防ごうとします。自然と猫背になりやすく、悪い姿勢が続けば神経痛の悪化にもつながりかねません。
日頃から、立っているときも座っているときも、正しい姿勢をキープするように意識しましょう。
睡眠環境を整備する
身体を冷えから守るためには、睡眠環境の見直しも大切です。寒い場所で寝ると、睡眠時も身体が縮こまり、無意識のうちに疲労を溜め込みます。坐骨神経痛対策のみならず、心身の健康を保つ意味でも睡眠環境を整える必要があります。
身体を冷えから守るためには、下記のポイントに注意して過ごしやすい寝室を作りましょう。
・部屋や床の温度に注意する
・自分に合った寝具を揃える
・暖かいパジャマを着用する
日中と同じく、睡眠時も暖かい衣類で身体を冷えから守る必要があります。室温が低くなりやすい季節は、部屋や床の温度にも配慮します。
食事に気を配る
口にする食べ物・飲み物も、身体の状態に大きく影響する要素です。例えば高脂質の食品など、血液の循環を悪化させるものを集中的に摂取していないでしょうか。
身体を冷えから守るためには、血流の改善が必要です。食事に気を配り、身体を温めるといわれている食材や料理を取り入れましょう。
身体を温める食べ物の代表例として、カボチャやニンジンなど暖色系の食材があげられます。ほかにも納豆、ぬか漬けといった発酵食品も適しています。
ストレスを解消する
ストレスを溜め込まず、適度に解消することも身体の冷え対策におすすめです。ストレスは、自律神経の乱れにつながります。そもそも手足の冷えが、ストレスによる自律神経の乱れから起こっている場合もあります。
腰痛の症状において、約8割を占めるのは心因的・社会的ストレスに起因することの多い「非特異的腰痛」です。過度なストレスで自律神経が乱れれば、手足の冷えのみならず、腰痛の原因となる可能性も考えられます。
また、腰痛や手足の冷えが続けば、症状そのものがストレスになる方もいるのではないでしょうか。ストレスで症状が出て、精神的に追い詰められて悪化するといった悪循環に陥ります。
働き過ぎたり不満を溜め込んだりと無理をしている方は、一度リフレッシュする時間を設けることが大切です。好きなことをして、十分に休息をとりましょう。
坐骨神経痛の予防におすすめのストレッチ
坐骨神経痛の予防には身体を温めたり姿勢を正したりするほか、適度な運動も大切です。
ここでは、坐骨神経痛の予防におすすめのストレッチを紹介します。
股関節の ストレッチ
腰椎椎間板ヘルニアによる、坐骨神経痛の方におすすめのストレッチです。股関節の付け根のストレッチにより股関節の柔軟性を高められるため、腰にかかる負荷を軽減できます。
ストレッチの手順は、下記の通りです。
1.片膝立ちの姿勢になる
2.お腹に軽く力を入れ、骨盤を前方へ移動させる
3.股関節の付け根が伸びていることを意識しながら10秒キープする
4.元の姿勢に戻って、反対側も同様に行う
ストレッチをする際は、腰をそらさないよう注意しましょう。
膝を抱えるストレッチ
腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)や腰椎すべり症によって、坐骨神経痛が生じている方におすすめです。上記のような腰を反らす動作が困難な方でも、膝を抱えるストレッチなら負担を抑えつつ身体をほぐせます。
具体的なストレッチの手順は、下記の通りです。
1.仰向けに寝る
2.お尻の下に座布団または枕を敷く
3.両手で膝を抱える
4.両膝を胸のほうへ引き寄せる
膝が持ち上がりにくい方は、お尻の下に座布団や枕を敷くとスムーズにできるようになります。両膝をしっかりと胸の前まで引き寄せられる方は、座布団や枕を敷く必要はありません。
ストレッチするときは、両膝を折り曲げることのみに集中しないことが大切です。両膝を胸に付けることではなく、腰が丸まっているかどうかを意識しましょう。
梨状筋のストレッチ
梨状筋(りじょうきん)とは、股関節の動きに関わる筋肉です。腰から下の動きをサポートしており、梨状筋が硬くなると姿勢の悪さや坐骨神経の圧迫につながります。
猫背や坐骨神経痛を予防する方法として、梨状筋のストレッチがおすすめです。ストレッチの手順は、下記の通りです。
1.椅子に腰かける
2.右の足首を持ち上げて、左の太ももに乗せる
3.腰を軸に身体を折り曲げるように前傾する
4.1~4を繰り返し行う
前傾するときは、背中を丸めないように注意してください。腰部分で直角に曲がるイメージです。ストレッチ中は呼吸を止めないようにして、同じ動作を繰り返し行いましょう。
まとめ
坐骨神経痛は、身体が冷えていると痛みが悪化するおそれがあります。日頃から暖かい衣類や室温を意識して、身体を冷えから守ることが大切です。
運動する習慣がない方は、仕事や作業の合間などにできる、手軽な運動やストレッチを取り入れてはいかがでしょうか。立ったままや椅子に座った状態でもできるストレッチもあるので、適度に身体をほぐしましょう。