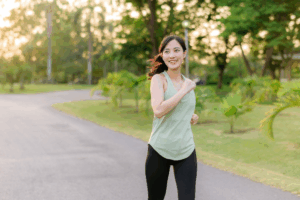理学療法士の健康相談室

股関節がゴリゴリする原因は?自宅でできる対処法も解説
歩いているときや立ち上がったときなどに、股関節にゴリゴリと擦れるような感覚があるという方もいるのではないでしょうか。その違和感は「弾発股(だんぱつこ)」かもしれません。弾発股は、放置すると炎症や痛みが悪化するおそれがあるため注意が必要です。 今回は、股関節がゴリゴリする違和感の原因や、対処法について解説します。
最終更新日: 2025.12.23
この記事は約4分で読み終わります。
股関節がゴリゴリするのは弾発股の可能性

股関節を動かしたときにゴリゴリと擦れるような感覚がある場合、「弾発股」を発症している可能性があります。
弾発股は、股関節まわりの靭帯や筋肉が骨に引っかかることで発症します。股関節を動かした際に違和感が生じたり、音(クリック音)が鳴ったりするのが主な症状です。
弾発股には、股関節の外側で起こる「外側型」と、内側で起こる「内側型」の2種類があります。
外側型の弾発股は、股関節の曲げ伸ばしをする際、太ももの外側にある腸脛靭帯(ちょうけいじんたい)が、股関節の横にある大転子(だいてんし)に引っかかることにより発症するのが特徴です。
一方、内側型は股関節の曲げ伸ばしで、腰から脚の付け根に付着する腸腰筋(ちょうようきん)が足の骨の先端にある大腿骨頭部で引っかかることにより生じます。
内側型が発症するケースは少なく、割合としては外側型のほうが多いといわれています。
また弾発股を発症しても、症状が軽いうちは痛みがなく生活に支障が出にくいため、放置してしまう方も少なくありません。
股関節がゴリゴリする原因とは

ここでは、股関節がゴリゴリする原因を解説します。
股関節を使い過ぎている
弾発股の原因として最も多いのは、股関節を使い過ぎているケースです。特に、激しいスポーツなどで股関節を頻繁に動かす方や、仕事で身体を酷使する方が弾発股を発症しやすいといわれています。
ランニングやサッカー、バレーボール、ダンス、バレエなどは注意が必要です。
股関節を繰り返し曲げ伸ばしする動作を頻繁に行っていると、気づかないうちに股関節に負担をかけている可能性があります。
股関節周辺の筋力が低下している
運動不足や加齢によって股関節まわりの筋肉が減少することも、弾発股を発症する原因です。
骨盤を支える股関節周辺の筋力が減少することで、身体に歪みが生じやすくなり、弾発股の発症のリスクが高まります。
特にお尻の筋力が低下すると、骨盤が不安定になって外側に動くため、弾発股を発症しやすくなります。
運動不足が原因で股関節の筋力が低下するケースも多いため、若い方でも注意が必要です。
骨盤が歪んでいる
骨盤が歪んでいると股関節が圧迫されるため、股関節の周囲にある筋肉が硬くなることがあります。
骨盤の歪みの原因は、猫背や足を組んで座るなど、姿勢の悪さや癖によるものが多いです。悪い姿勢を続けていると、徐々に骨盤に歪みが生じ、身体の左右のバランスが崩れます。
そうなると、普段使われにくいほうの筋肉が硬くなり、靭帯や腱が引っかかりやすくなるのです。
骨盤の歪みは普段の生活習慣が大きく影響しているため、姿勢や何気ない癖などを意識して過ごす必要があります。
股関節そのものが変形している
股関節そのものの形状が変形しており、靭帯や腱が引っかかりやすくなっていることが原因の場合もあります。
股関節が変形する原因には、生まれつきの形状である場合や、股関節の使い過ぎによる変形の場合などもあります。
また、股関節の変形の代表的な疾患である「変形性股関節症」を発症すると、最初は歩き始めや立ち上がりに脚の付け根に痛みを感じ始め、進行すると痛みが徐々に強くなります。
股関節の変形を放置すると悪化するおそれもあるため、心当たりのある方は早めに病院を受診してください。
股関節がゴリゴリするのを放置するとどうなる?
弾発股を発症しても、初期の段階では音がするだけで痛みがない場合がほとんどです。
しかし、弾発股を放置し続けると、股関節の骨に靭帯や腱が何度も引っかかることで、炎症が起こり痛みをともなうようになります。
痛みを放置すると股関節が変形するリスクがあるため、日常生活に支障をきたすおそれもあります。また、仮に弾発股が自然に治まったとしても、再発するケースも少なくありません。
そのため、股関節に痛みや違和感があったら、早急に医療機関へ受診することが重要です。
股関節がゴリゴリするときの対処法

ここからは、股関節がゴリゴリするときの対処法を解説します。
休息を十分にとる
股関節に違和感や痛みがあるときは、無理せず安静にしましょう。
弾発股の原因のひとつが過度な運動であるため、運動量が多すぎる場合はいったん休み、安静期間をつくるのが良いでしょう。
強い痛みがある場合は病院の受診も検討し、消炎鎮痛剤などで痛みを抑えるのも重要です。また、股関節まわりの炎症を抑えるためには、運動後にアイシング(冷却)をするのもおすすめです。
万が一痛みが治まったとしても、回復するまでしっかり休まないと再発することもあります。治るまで時間がかかっても焦らず、様子をみながら安静に過ごしましょう。
座り方や歩き方を改善する
正しくない歩き方や座り姿勢をしていると股関節に負担がかかるため、弾発股を発症しやすくなります。
特に、歩く際にガニ股になっていたり、座った際に猫背になったりする場合は要注意です。
歩く際にガニ股になっている場合は、内ももの筋肉を鍛えるのが有効です。横向きの姿勢で横になり、上の脚を下の脚の前で折り曲げます。この状態で、下の足を上げたり下げたりする動作を繰り返してみましょう。
また猫背が気になる方は、簡単な胸のストレッチがおすすめです。背中で手を組み、肩甲骨を寄せるようにして胸を開き、15〜30秒ほど維持します。これを1日に数回行いましょう。
歩き方や姿勢が改善されると、股関節への負担を抑えられるだけでなく、弾発股以外の痛みや不調にも効果が期待できます。
ストレッチや筋トレをする
ここでは、弾発股の改善を目指すためのストレッチや筋トレを3つ紹介します。
腸腰筋(ちょうようきん)のストレッチ

腸腰筋は、大腿骨から背骨にかけて付着する筋肉です。腸腰筋は足を上げたり、歩いたりする動作に関わっています。
- 片膝立ちの姿勢になる
- 前方の足に体重をのせる
- 元の姿勢に戻る
- 1~3を繰り返し実施する
股関節まわりのストレッチ

股関節まわりの筋力を適度に刺激すると、血液の流れを促したり、股関節を安定させたりする効果が期待できます。
- 椅子に座った状態で両脚を大きく広げる
- 両手を両膝につけて、上半身を前方に倒す
- 元の姿勢に戻る
- 1~3を繰り返し実施する
上記のストレッチの際は、腰が曲がらないように注意して、内ももが伸びているのを感じながら行いましょう。
大殿筋(だいでんきん)のストレッチ

大殿筋は、股関節周辺にある筋肉のなかで最も大きな筋肉です。股関節の伸展や外旋などの役割を持っています。
- 四つん這いの姿勢になる
- お尻を斜め後方へ動かす
- 元の姿勢に戻る
- 1~3を繰り返し実施する
医療機関で相談する
ここまで紹介したセルフケアを続けても、股関節の痛みやゴリゴリという違和感が治まらないという場合は、弾発股以外の症状が原因の可能性もあります。
症状をきちんと見極めるためには、医療機関を受診しましょう。レントゲンやMRIなどの精密な検査によって、正確な診断を受けられます。
まとめ
股関節を動かしたときにゴリゴリと音がなる場合、弾発股を発症している可能性があります。弾発股の原因は、股関節の使い過ぎや筋力の低下、骨盤の歪みなどです。
放置すると炎症や痛みが悪化し、日常生活に支障をきたすおそれがあるため注意が必要です。
セルフケアで緩和できる場合もありますが、医療機関を受診し、医師の指示に従い適切な治療を受けると良いでしょう。
関連記事
RELATED POSTS
注目キーワード
KEYWORD
監修

M&メディカルリハ
株式会社
執行役員
髙見 友
(たかみ ゆう)
保有資格
- 理学療法士
- 日本理学療法士協会会員
- Certified Fascial Manipulation® Specialist (CFMS)
- ドイツ徒手医学認定セラピスト 2016年取得
- 認定理学療法士 運動器領域 2019年取得
経歴
- 2008年
- 千葉・柏リハビリテーション学院卒業
- 2008年
- いちはら病院勤務
- 2018年
- あかおぎ整形外科クリニック勤務
- 2019年
- M&メディカルリハ株式会社 執行役員就任