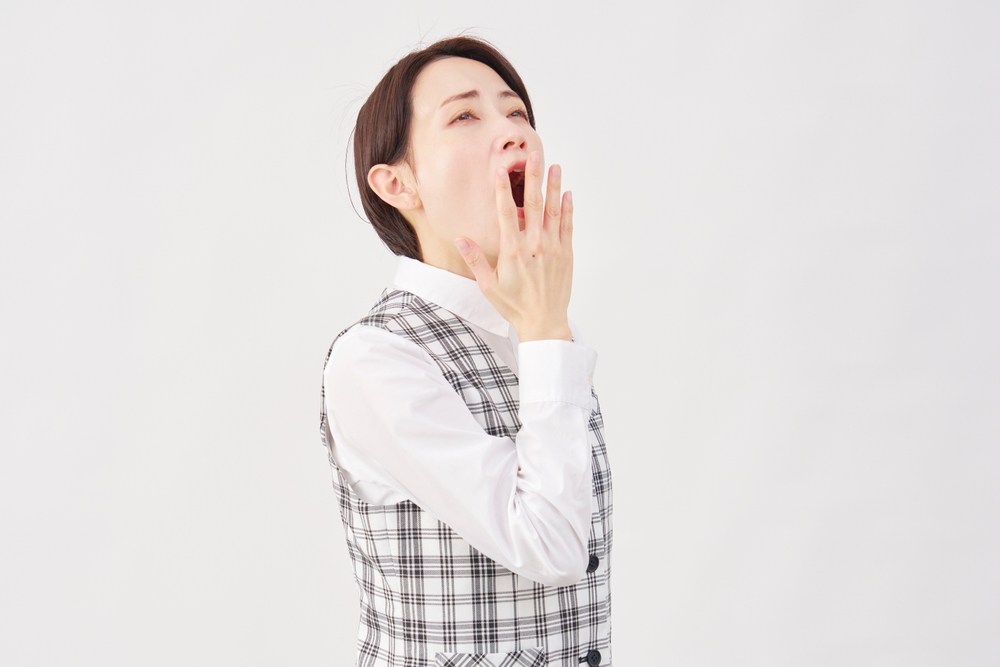日常生活の中で考えられる眠気の原因
「しっかり寝たはずなのに、なぜか眠い……」そんなときは、日常生活の中に原因が隠れているかもしれません。
ここでは、寝ても眠気が取れない場合に考えられる主な要因について解説します。
睡眠不足
日中の眠気の大きな原因として、まず考えられるのが睡眠不足です。
成人に必要とされる睡眠時間は、一般的に7~8時間程度とされていますが、日本人の平均睡眠時間は6~7時間とやや短めです。
睡眠不足の背景として、代表的な要因と思われるのが多忙なライフスタイルでしょう。忙しさのあまり十分な睡眠時間が確保できなかったり、ストレスによって寝つきが悪くなったりするなど、知らず知らずのうちに慢性的な睡眠不足を引き起こしている場合があります。
睡眠環境
睡眠時間は足りているのに眠い場合は、睡眠の質が低下している可能性があります。睡眠の質を左右する大きな要素のひとつが睡眠環境です。
寝室の温度や湿度が高すぎたり低すぎたりすると、寝つきが悪くなったり眠りが浅くなったりします。また、照明が明るすぎたり、騒音が気になったりする場合も、途中で目が覚めてしまう原因になります。
こうした環境要因によって、熟睡できず「寝ても寝ても眠い」状態になってしまうのです。
生活習慣
睡眠の質は、生活リズムとも深く関係しています。毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きるという規則正しい生活は、良質な睡眠を促します。
反対に、就寝・起床時間が日によってバラバラだったり、夜勤やシフト勤務で不規則な生活をしたりしていると、寝たいと思ってもなかなか寝つきにくいものです。そのため、快眠が得られず、日中に眠気を引き起こしやすくなります。
また、過度な飲酒や喫煙も睡眠の質を下げる原因となるため、注意が必要です。
ストレス
精神的・身体的なストレスも、眠気の原因として無視できません。ストレスがかかると、自律神経のうち交感神経が優位になり、脳や身体が興奮状態となります。
この状態では寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりするため、睡眠時間を確保していても疲れが取れず、日中の眠気を感じやすくなります。
即効性が期待できる眠気の対策
本来であれば、眠気の原因をみつけて対処することが重要です。しかし、「今すぐなんとかしたい!」という状況もあるでしょう。
仕事中や授業中に眠くなってしまったとき、すぐに試せる眠気対策を知っておくと安心です。
ここでは、即効性のある眠気覚ましの方法をいくつか紹介します。
カフェインを摂取する
強い眠気を感じたときは、カフェインの摂取が効果的です。コーヒーや紅茶、エナジードリンクなどに含まれるカフェインには、脳を覚醒させる働きがあります。
また、薬局で購入できるカフェイン含有の医薬品も、眠気対策に有効です。
ただし、カフェインの過剰摂取は逆に睡眠の質を下げることがあるため、適量を守ることが大切です。
短時間の仮眠をとる
どうしても眠気が取れないときは、短時間の仮眠をとるのが効果的です。無理に起きているよりも、いったん眠ってリフレッシュしたほうが、その後のパフォーマンスが向上します。
仮眠の目安は「15分以内で15時まで」です。
それ以上の長さだとかえってボーっとしてしまったり、遅い時間の昼寝は、夜の睡眠に悪影響を与えたりする可能性があります。お昼休憩の時間を活用するのがおすすめです。
身体を動かす
座りっぱなしの状態が続くと、血流が滞り、眠気を感じやすくなります。そんなときは、ストレッチや軽い運動をして身体を動かしましょう。
肩を回す、軽く屈伸する、少し歩くなど、簡単な動きでも眠気を和らげる効果が期待できます。仕事や勉強の合間に、意識して取り入れてみてください。
ツボを押す
東洋医学では、眠気を覚ますツボがあるとされています。手軽に試せる対策としてツボ押しはおすすめです。
下記のツボは、眠気覚ましに効果的といわれています。
・風池(ふうち):耳の後ろの骨の外側、髪の生え際のくぼんだ部分
・中衝(ちゅうしょう):中指の爪の人差し指側、生え際から約2ミリ下
・合谷(ごうこく):手の甲、親指と人差し指の骨が交差する部分のくぼみ
指先で軽く押したり、マッサージするように刺激したりしてみましょう。
眠気の予防のために心がけたいこと
日中の眠気を防ぐには、日頃の生活習慣を見直すことが大切です。ここでは、眠気の予防につながる習慣や意識したいポイントを紹介します。
同じ時刻に毎日起床する
体内時計(概日リズム)を整えるには、毎日同じ時間に起きることが効果的です。起床時間を一定にすることで、睡眠と覚醒のリズムにメリハリがつき、日中の眠気が軽減されます。
「早寝早起き」は理想的ですが、いきなり早く寝ようとしても寝つけないこともあるでしょう。その場合は、まずは早起きを習慣化することから始めてみましょう。朝の活動が整えば、自然と夜も早く眠れるようになります。
日中は日光を浴びる
目が覚めたらすぐにカーテンを開けて朝の光を浴びることで、体内時計をリセットすることができます。
睡眠を促すホルモン「メラトニン」は、光を浴びると分泌が抑制され、そこから約14時間後に再び分泌が始まります。つまり、朝に光をしっかり浴びることで、夜に自然な眠気が訪れやすくなるのです。
規則正しい3度の食事をする
朝・昼・夜の規則正しい3食は、体調管理だけでなく睡眠の質にも関係しています。特に朝食は、身体と脳を目覚めさせる上で重要です。
また、栄養バランスが偏るとエネルギー不足になり、眠気を引き起こす要因にもなり得ます。糖質・脂質・タンパク質の三大栄養素に加え、代謝を助けるビタミンB群も意識して摂取しましょう。
栄養が不足しがちな方は、サプリメントを活用するのもひとつの方法です。
規則的な運動をする
適度な運動には、眠りの質を高める効果があります。ウォーキングやジョギング、ストレッチなどの軽い運動を毎日続けると、寝つきが良くなり、深い眠りが得られやすくなります。
運動のタイミングは、夕方〜夜の早い時間帯がおすすめです。寝る直前の激しい運動は交感神経を活発にしてしまうため避けましょう。
寝る前は刺激物を避ける
快適な睡眠のためには、寝る前の過ごし方にも注意が必要です。カフェインは就寝の4時間前から、喫煙は1時間前から控えるようにしましょう。
代わりに、軽い読書や音楽を楽しむことができます。また、ぬるめのお風呂(38~40℃)に15~20分程度つかると、リラックスできてスムーズに入眠しやすくなります。
それでも治まらない場合は過眠症かも?
さまざまな対策を試しても「どうしても眠い」「眠気が取れない」という場合は、過眠症という病気の可能性があります。
過眠症とは、夜間に十分な睡眠をとっていても、日中に強い眠気が繰り返し現れ、生活に支障をきたす病気です。睡眠時無呼吸症候群などの睡眠を妨げる別の病気が原因でないにもかかわらず、眠気が続くのが特徴です。
ここでは、代表的な3つの過眠症について解説します。いずれも専門医による診断と治療が必要ですので、心当たりがある場合は早めの受診を検討しましょう。
ナルコレプシー
日中に強い眠気に襲われ、短時間の居眠りを繰り返してしまう病気です。眠気は10~20分程度の短時間で、どんな状況でも突然眠り込んでしまうのが特徴です。
例えば、食事中や会話中など、通常であれば眠らない場面でも発作的に眠ってしまうことがあります。
このような症状は、日常生活や仕事、学業に影響を及ぼすことがあり、集中力の低下や不注意によって思わぬ事故のリスクも高まるため、気になる場合は早めに医師に相談することが大切です。
特発性過眠症
主な症状は、日中の強い眠気と、長時間の睡眠でもスッキリと目覚められないことです。
ナルコレプシーに比べると眠気の強度はやや弱いものの、一度眠りにつくと1時間以上起きられないケースもあります。
反復性過眠症
1日の大半を眠り続ける状態(傾眠期)が数日から数週間にわたって続き、これが年に1回以上起こる病気です。
傾眠期の間は1日16時間以上眠ることもあり、非現実感(夢の中にいるような感覚)や、食欲・性欲の極端な変化などの症状をともなうこともあります。
まとめ
しっかり寝ているのに眠い状況が続く場合、まずはその原因を見極めることが大切です。多くのケースでは、睡眠不足や生活習慣の乱れ、睡眠環境、ストレスなど、日常生活に要因が潜んでおり、これらを見直すことで改善が期待できます。
また、カフェインの摂取や仮眠、軽い運動、ツボ押しなどで一時的に眠気をやわらげるのも有効です。
それでも改善がみられない、どうしても眠くてつらいという場合は、過眠症などの病気が隠れている可能性もあります。日常生活に支障をきたすほどの眠気を感じる場合は、早めに医師に相談しましょう。