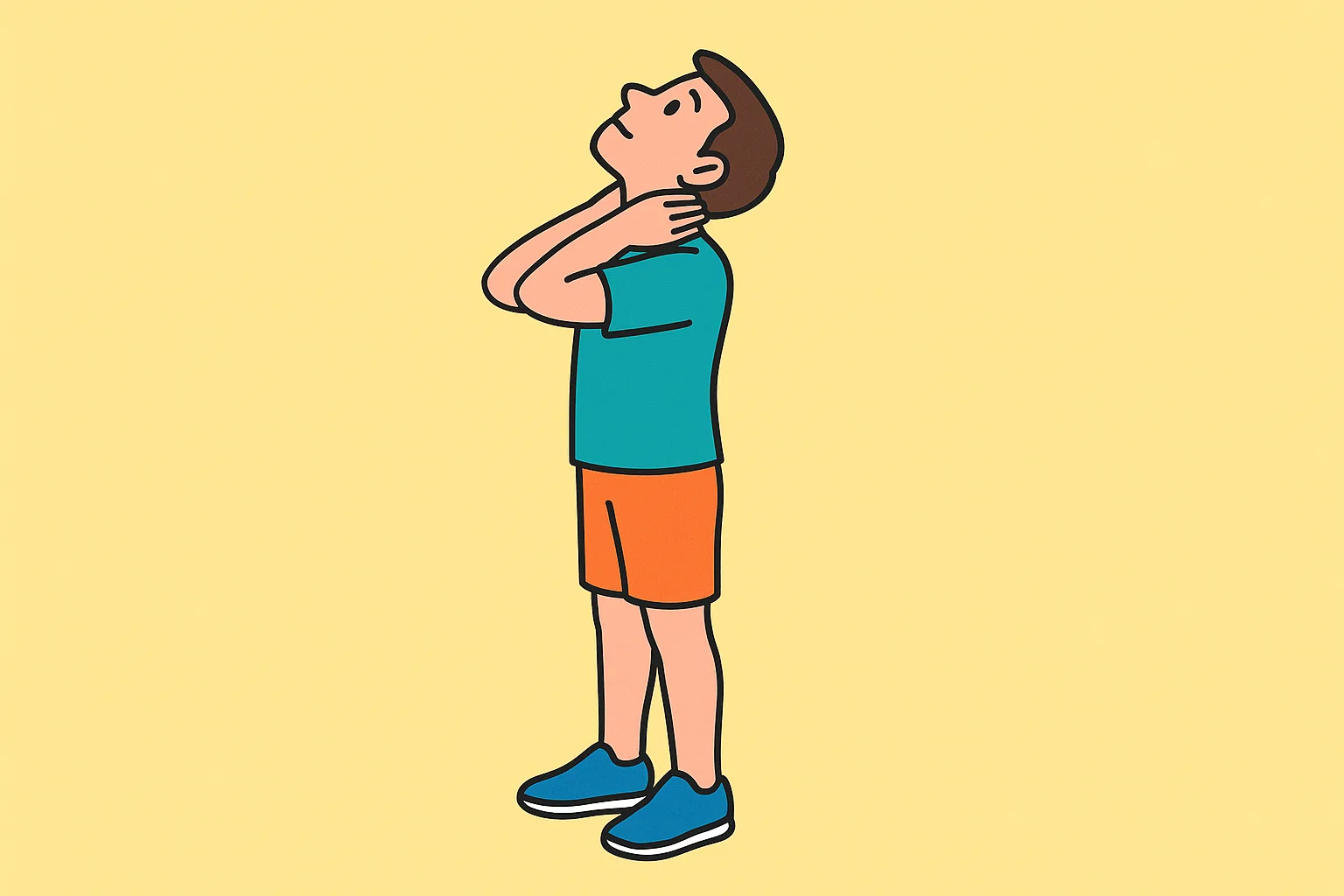こめかみが痛くなる原因は3つ
こめかみの痛みは、大きく分けて「片頭痛」「緊張型頭痛」「群発頭痛」の3つが代表的です。それぞれ症状の出方や原因が異なるため、自分の痛みの特徴を知っておきましょう。ここでは、それぞれの特徴について詳しく紹介します。
ズキズキ痛む場合|片頭痛
こめかみがズキズキと脈打つように痛む場合は、片頭痛が疑われます。片頭痛は頭の片側に起こることが多く、吐き気や嘔吐、下痢をともなうケースもあります。また、光や音、においに敏感になるのも特徴です。
片頭痛の原因はさまざまで、ストレスや睡眠不足、ホルモンバランスの乱れなどが大きく影響するといわれています。加えて、人によっては特定の食べ物や天候、生活習慣の変化が引き金になることも少なくありません。そのため、自分の誘因を知り、できるだけ避けることが対策のポイントです。
締め付けるように痛む場合|緊張型頭痛
こめかみがギューッと締め付けられるように痛むときは、緊張型頭痛が考えられます。片頭痛とは異なり、吐き気や光・音への過敏な反応が起こることはほとんどありません。
主な原因は、肩や首まわりの筋肉が凝り固まり、血流が悪くなることにあります。PCやスマートフォンを長時間使用するなど筋肉が緊張しやすい環境が続くと、頭痛が引き起こされやすくなって緊張型頭痛の症状が出るのです。日頃から姿勢を意識したり、身体をこまめに動かしたりして筋肉のコリを防ぐことが大切です。
激しい痛みが繰り返される場合|群発頭痛
こめかみや目の奥に我慢できないほど強い痛みが繰り返されるときは、群発頭痛の可能性があります。原因は、はっきり解明されていませんが、脳神経や血管の異常が関係していると考えられています。
数週間から数か月にわたり、決まった時間帯に毎日のように激しい痛みが起こるのが特徴です。さらに、目の充血や鼻づまり、発汗、まぶたの腫れなどの症状がともなうこともあります。セルフケアでの改善は難しいため、群発頭痛が疑われる場合は早めに専門医の診察を受けましょう。
こめかみが痛いときのセルフケア
こめかみの痛みは原因によって対処法が異なるため、症状に合わせたセルフケアを行いましょう。ここでは片頭痛と緊張型頭痛、それぞれの対処法を紹介します。
片頭痛の場合
片頭痛によるこめかみの痛みは、刺激を避けて安静に過ごすことが基本です。症状を和らげるために効果的な対処法を紹介します。
患部を冷やす
片頭痛が起きているときは、こめかみや額を冷やすと痛みを和らげやすくなります。冷たいタオルや保冷剤を使い、刺激を与えないよう優しく当てるのがポイントです。冷やすことで血管の拡張が抑えられるので、症状の緩和が期待できます。
暗室で横になり休む
片頭痛が起きているときは、光や音などの刺激をできるだけ避けることが大切です。明るい場所や騒がしい環境は症状を悪化させる原因となるため、暗く静かな部屋で横になって安静に過ごしましょう。
目を閉じてリラックスすると、痛みが和らぐ場合があります。無理に動かず、身体をしっかり休めることを意識してください。
ツボを押す
片頭痛によるこめかみの痛みを和らげたいときは、ツボ押しも効果的な方法のひとつです。首にある「風池(ふうち)」や手の「合谷(ごうこく)」というツボを、心地良いと感じる強さでゆっくり押してみましょう。
痛みが和らぐ他、リラックス効果も期待できます。無理に強く押さず、呼吸を整えながら優しく刺激するのがポイントです。
緊張型頭痛の場合
緊張型頭痛によるこめかみの痛みは、血行を促したり筋肉のコリをほぐしたりすることで改善が期待できます。
首や肩を温める
緊張型頭痛は、肩や首まわりの筋肉が凝り固まることで血流が悪くなり、痛みが引き起こされます。そのため、蒸しタオルや温熱シートを使って首や肩を温めると血行が促進され、筋肉の緊張が和らぐでしょう。
また、入浴をするのも効果的です。心地良いと感じる温度でゆっくり温め、リラックスしながらケアしましょう。
身体を動かす
長時間同じ姿勢でいると、筋肉が緊張して血流が悪くなり、緊張型頭痛を引き起こしやすくなります。こめかみの痛みを感じたときは、軽いストレッチやウォーキング、肩回し、首をゆっくり動かすなどの運動をすると効果的です。
無理に激しい運動をする必要はありません。身体をほぐすようにゆったりと動かすと、血流が改善され、痛みの緩和につながります。
スマホやパソコンの使用を控える
スマートフォンやPCを長時間使用していると、無意識のうちに前かがみの姿勢が続き、首や肩に大きな負担がかかります。この状態が続くと血流が悪くなり、緊張型頭痛が起こりやすくなります。
こめかみに痛みを感じたときは、スマートフォンやPCの使用を控え、目や身体を休める時間をつくることが大切です。作業が続く場合でも、適度に休憩を取り、姿勢を整えるようにしましょう。
こめかみの痛みを予防する方法
こめかみの痛みを繰り返さないためには、日ごろからの予防が重要です。原因に合わせた対策をすれば、痛みの発生を防ぎやすくなります。ここでは、片頭痛と緊張型頭痛、それぞれに効果的な予防法を紹介します。
片頭痛の予防法
片頭痛は、生活習慣や環境の工夫によって発症リスクを軽減できます。自分に合った予防法を行い、症状を防ぐことを目指しましょう。
片頭痛の誘因を特定してなるべく避ける
片頭痛は、人によって引き金となる誘因が異なるため、自分のパターンを知ることが予防の第一歩です。天候の変化や寝不足、ストレス、特定の食べ物や飲み物がきっかけになることもあります。
頭痛が起きたときは、その前後の行動や環境をメモしておくと誘因を特定しやすいでしょう。原因がわかれば、それを避ける工夫をすることで片頭痛の発症を抑えやすくなります。
しっかりと睡眠をとる
片頭痛を予防するためには、質の良い睡眠をしっかりとることが大切です。睡眠不足はもちろん、寝すぎも頭痛の引き金になることがあるため、毎日同じ時間に寝起きする規則正しい生活を心がけましょう。
寝る前のスマートフォンやPCの使用を控え、リラックスした状態で眠りにつける環境を整えることもポイントです。
食事にも気を配る
チョコレートやチーズ、赤ワインなどは、人によって頭痛の誘因になります。また、空腹状態が続くと血糖値が低下し、頭痛を引き起こしやすくなるため、お腹がすいたと感じたら何か軽く食べるようにしましょう。
規則正しくバランスの取れた食事を心がけ、カフェイン飲料やアルコールはできるだけ避けるようにしましょう。
コマ体操をする
片頭痛の予防には、肩や首の血流を良くする「コマ体操」が効果的です。下記の手順に沿って実践してみましょう。
【手順】
1.正面を向き、立つ場合は足を肩幅に開き、座る場合は軽く足を開いてリラックスした姿勢をとります。
2. 頭は正面に向けたまま動かさないように意識します。
3. 両肩を大きく回し、左右の肩を交互に90度まで前へ突き出すように動かします。
4. 頚椎(首の骨)を軸にして、コマのようにリズミカルに身体を回転させましょう。
5. 最大2分間を目安に、無理のない範囲で行います。
腕の力は抜き、身体の軸を意識しながら行うのがコツです。笑顔でリラックスしながらテンポ良く続けると、脳への刺激が高まりやすくなります。
普段あまり動かさない筋肉を使うため、長時間行うのは逆効果です。1日2分を目安に、毎日の習慣として取り入れましょう。
緊張型頭痛の予防法
緊張型頭痛は、日ごろの生活習慣や身体の使い方を意識すると予防が可能です。肩や首のコリを起こさないための工夫を紹介します。
正しい姿勢を意識する
猫背や前かがみの姿勢は、首や肩に負担がかかり、筋肉がコリやすくなります。背筋を伸ばし、耳・肩・腰が一直線になる姿勢を心がけましょう。
デスクワーク中は、椅子に深く腰かけ、足裏をしっかり床につけるのもポイントです。姿勢を整えると、肩や首への負担が軽減され、頭痛の予防につながります。
血流を改善する生活を心がける
緊張型頭痛は、血流の悪化によって筋肉が凝り固まりやすくなることが原因のひとつです。普段から適度な運動やストレッチを行い、身体をこまめに動かしましょう。
湯船につかって、身体を温める習慣も血行促進に効果的です。また、冷えは血流を悪くする原因になるため、首や肩を冷やさないよう意識しましょう。
コンディショニングを行う
緊張型頭痛の予防には、首や肩まわりの筋肉を和らげる「コンディショニング」が効果的です。すきま時間に簡単にできる運動法で、筋肉の緊張をほぐしましょう。
【ステップ1】
1.椅子に座り、リラックスした姿勢をとります。首を軽く下に倒したときに、首の後ろ側で少し出っ張っている骨(頚椎の上部)を指(人差し指から小指まで)でやさしく押さえます。このとき、手のひら全体が首の側面にしっかりフィットするように当てるのがポイントです。
2. そのままの姿勢を保ちながら、うなずく動作をするように頭を小さく上下に動かします。無理のない範囲で、ゆっくりとリズム良く繰り返しましょう。
3. 続けて、首を左右に小さく振る動きを行います。左右それぞれ10回ずつを目安に、ゆっくりと動かしていきましょう。
【ステップ2】
1.手の人差し指から小指までを使い、首の後ろ側にある骨(頚椎)を支えるように優しく押さえます。あごをゆっくり引いて、無理のない範囲で心地良く感じる位置で止めましょう。
2.そのままの姿勢をキープし、首の後ろ側の筋肉を意識しながら、あごを持ち上げるようにしてゆっくりと上を向きます。この動きは30回を目安に、無理のないペースで繰り返しましょう。
こめかみが痛くて受診が必要なケース
こめかみの痛みが長期間続いている場合や、これまでに経験したことのない強い痛みを感じるときは、早めに医療機関を受診してください。
さらに、痛みに加えて手足のしびれやめまい、ろれつが回らないといった症状が現れる場合は注意が必要です。
これらの症状は、脳や神経に関わる病気が隠れている可能性もあるため、自己判断で放置せず、早めに専門医に相談するようにしましょう。
まとめ
こめかみの痛みは、片頭痛や緊張型頭痛など原因によって対処法が異なります。症状が軽い場合はセルフケアで改善が期待できますが、痛みが続いたり、他の症状をともなったりする場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。日ごろから予防を心がけ、頭痛に悩まない生活を目指しましょう。
【関連記事】
おでこ周辺に頭痛が……考えられる原因と対処法を解説