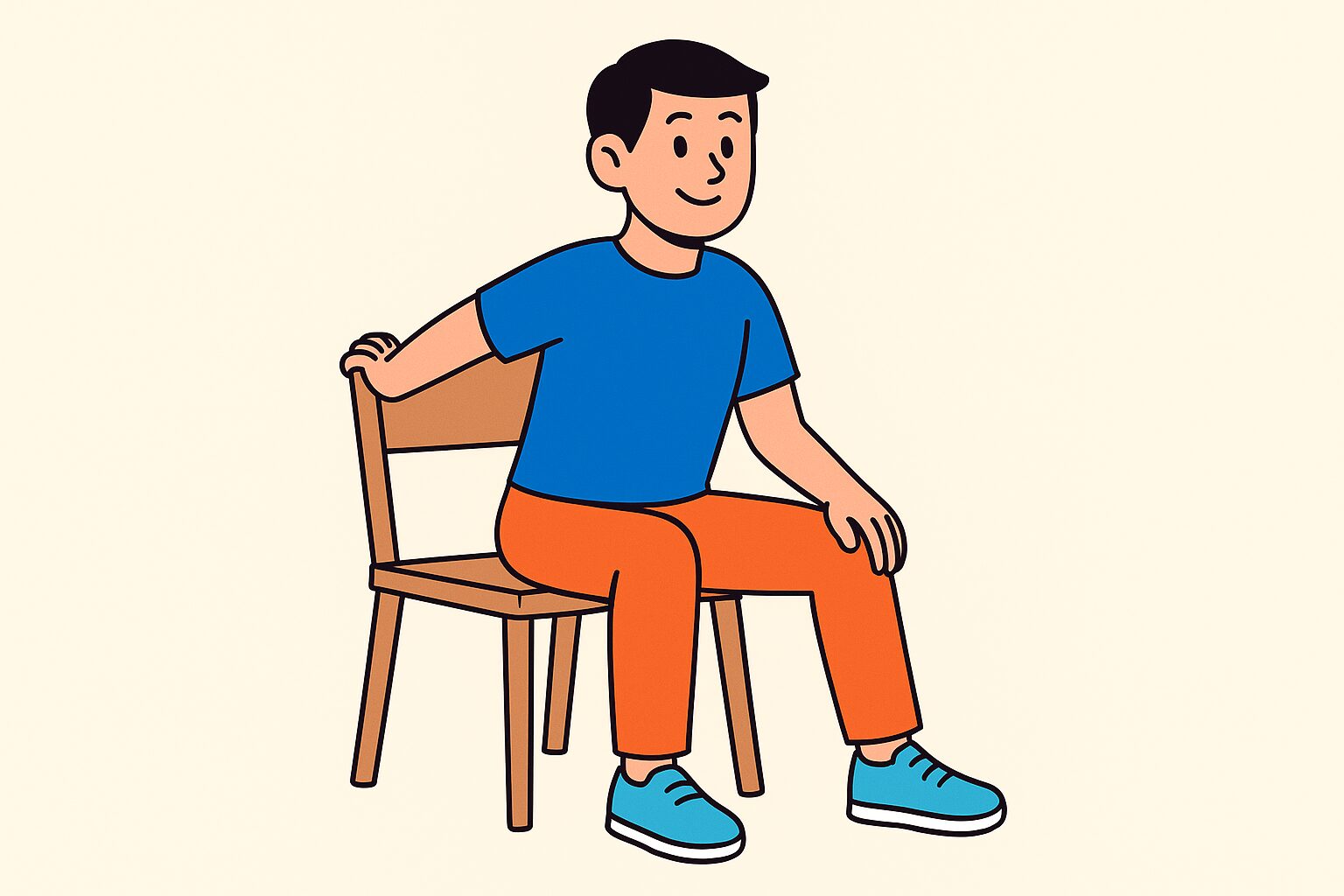いかり肩とはどんな状態?
いかり肩とは、鎖骨の角度が水平より斜め上に向いた状態のことです。鏡の前で鎖骨の角度を確認すれば、いかり肩かどうか簡単にチェックできます。
鎖骨の傾きが9時15分から10時10分の範囲内かつ水平に近い状態であれば、正常であると考えられます。一方、鎖骨の角度が10時10分の位置より上がっていれば、いかり肩の可能性があるでしょう。
いかり肩となで肩の違い
なで肩とは、鎖骨の角度が水平より斜め下に向いている状態のことです。鏡の前でチェックしたとき、鎖骨の傾きが9時15分の角度より下がっている場合はなで肩の可能性があります。
なで肩の方は首が長く見える一方、肩にかけた鞄がずり落ちる、肩が凝りやすい、などのデメリットがあります。
いかり肩によくある悩み
いかり肩は鎖骨の外側が上を向き、肩が常に上がっている姿勢です。そのため、背中から首、肩甲骨にかけて広がる僧帽筋上部(そうぼうきんじょうぶ)や、肩甲骨を上に引き上げる肩甲挙筋(けんこうきょきん)が緊張して凝り固まり、肩こりを引き起こしやすくなります。
また、肩が上がることで肩幅が広く見えたり、上半身がガッチリしているような印象を与えたりなど、見た目の悩みにもつながります。和服やウエディングドレスがしっくりこない、襟ぐりが詰まった服を着るとのっぺり感が出る、といったファッションの悩みをもつ方も少なくありません。
いかり肩の原因
いかり肩の原因は骨格や筋肉のつき方などの遺伝的な要素もありますが、生活習慣が関係している場合もあります。
ここでは、日常生活で生じる後天的な原因について解説します。
不良姿勢
日頃の姿勢が悪いと、いかり肩になる可能性があります。特にPCやスマートフォンの使用中に無意識に肩が上がっている方は筋肉の緊張が強くなり、いかり肩になりやすいといえるでしょう。
また、デスクワークの作業環境が整っていない場合も肩に過度な負担がかかりやすくなります。例えば、キーボードの位置が高すぎると両腕を持ち上げた姿勢になり、肩に力が入った状態が続きます。その結果、筋肉の緊張や血流の悪化を招いてしまうのです。
体格に合わせて机や椅子の高さを調整し、肩に力が入らない状態で作業を行いましょう。
筋肉の緊張・筋力低下
筋肉の緊張や筋力の低下も、いかり肩の原因です。肩まわりの筋肉である僧帽筋上部や肩甲挙筋が緊張し続けていたり、収縮していたりすると、いかり肩を引き起こしやすくなります。
また、長時間の同じ姿勢や運動不足によって僧帽筋が衰えることも、いかり肩の原因のひとつです。
いかり肩を改善するセルフケア
遺伝的な要素で生まれつきいかり肩の方はセルフケアでの改善が難しいものの、生活習慣が原因であれば改善が見込めます。
ここでは、自分でいかり肩を改善する方法を3つ紹介します。
正しい姿勢を意識する
姿勢が悪いといかり肩になりやすいため、日頃から正しい姿勢を心がけることが大切です。立っているときの良い姿勢とは、耳・肩・腰・膝・くるぶしが一直線になる状態のことを指します。お腹に力を入れて骨盤を立て、肩甲骨を軽く後ろに引いて背筋を伸ばしましょう。
また、座っているときも耳・肩・骨盤の位置が一直線になるように意識し、頭から糸で吊るされているイメージで背筋を伸ばすのがポイントです。
デスクワーク中は無理のない姿勢で作業を行えるよう、机や椅子、ディスプレイ、キーボード、マウスを適切な位置に配置しましょう。キーボードは肘と同じ高さに置き、腕は力を抜いて自然に下ろします。作業環境や姿勢を整えることで肩や腕、首への負担を軽減でき、いかり肩の改善だけでなく肩こり・首こり・腰痛の予防にもつながります。
また、長時間座り続けると肩まわりの筋肉が凝り固まってしまうため、30分~1時間に1回は立ち上がり、身体を伸ばしたり歩いたりしましょう。
肩まわりのストレッチを行う
いかり肩の改善には、肩を引き上げる筋肉をストレッチすることが重要です。凝り固まった肩まわりの筋肉をほぐすことが大切です。
ここでは、僧帽筋上部や肩甲挙筋をほぐす簡単なストレッチを紹介します。身体が温まり、筋肉がやわらかくなっている入浴後に、ぜひストレッチを取り入れてみましょう。
僧帽筋上部線維のストレッチ
<右側のストレッチ>
1.椅子に座り、右手で椅子の斜め後方をつかむ
2.首を左に倒し、右に回す
3.この状態で1分キープし、首をもとの位置に戻して15秒休憩する
4.1~3の流れを3セット行う
首を右に回す際は、左耳が肩より前に出るようにしましょう。左手で少し頭を押さえるとストレッチ効果が高まりますが、強い力を加えないように注意してください。
<左側のストレッチ>
1.椅子に座り、左手で椅子の斜め後方をつかむ
2.首を右に倒し、左に回す
3.この状態で1分キープし、首をもとの位置に戻して15秒休憩する
4.1~3の流れを3セット行う
肩甲挙筋のストレッチ
<右側のストレッチ>
1.椅子に座り、右手で椅子の斜め後方をつかむ
2.首を左に倒し、左に回す
3.この状態で1分キープし、首をもとの位置に戻して15秒休憩する
4.1~3の流れを3セット行う
首を左に回すとき、鼻を肩に近づけるようにするのがポイントです。左手を頭に乗せ、首を痛めない程度に押さえるとストレッチ効果が高まります。
<左側のストレッチ>
1.椅子に座り、左手で椅子の斜め後方をつかむ
2.首を右に倒し、右に回す
3.この状態で1分キープし、首をもとの位置に戻して15秒休憩する
4.1~3の流れを3セット行う
いずれのストレッチも座ったまま行えるため、デスクワークの合間や休憩中にもおすすめです。
毎日少しずつでもストレッチを継続することで筋肉の柔軟性を保ちやすくなり、ストレスの軽減やリラックス効果も期待できます。
肩まわりの筋トレを行う
筋トレで肩を引き下げる筋肉にアプローチすることで、いかり肩の改善が期待できます。
ここでは、僧帽筋下部線維を強化するトレーニングを紹介します。
僧帽筋下部線維の筋トレ(その1)
立った状態・座った状態のどちらでも行える僧帽筋下部線維のトレーニングを紹介します。
1.両肘を肩の高さまで上げる
2.両肘と肩甲骨を一緒に引き下げ、そのまま5秒間キープ
3.両肘を肩の高さまで戻す
4.1~3を10回繰り返す
僧帽筋下部線維を鍛えることで、大胸筋や小胸筋、広背筋のストレッチも行えます。最初は無理のない範囲で行い、余裕が出てきたら回数を増やしましょう。
僧帽筋下部線維の筋トレ(その2)
続いて、立った状態で行う僧帽筋下部線維の筋トレを紹介します。
1.壁の前に立ち、両腕を11時5分の角度に上げる
2.手の甲を壁に当てる
3.手の甲を壁から離し、5秒キープ
4.2~3を10回繰り返す
肩甲骨と上半身の動きを意識し、お腹に力を入れるのがポイントです。慣れてきたら徐々に回数を増やしていきましょう。
まとめ
いかり肩の主な原因は、不良姿勢・長時間の同じ姿勢による筋肉の緊張や筋力低下です。いかり肩になると肩が常に上がった状態になり、肩こりや首こりを起こしやすくなります。また、肩が上がることで上半身がガッチリして見えたり、肩ラインが強調される服を楽しめなくなったりなどの悩みも生じます。
日頃から正しい姿勢を心がけるとともに、今回紹介したストレッチや筋トレも取り入れ、いかり肩の改善を目指しましょう。